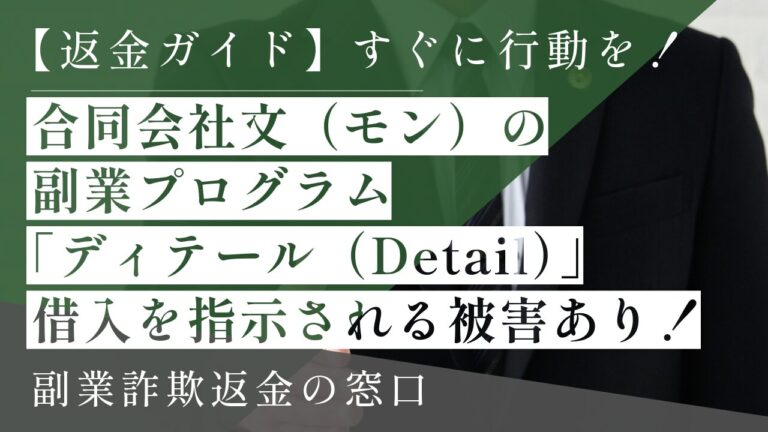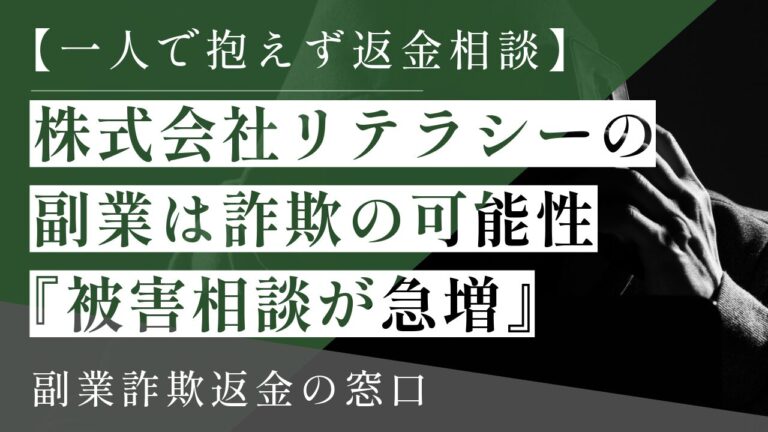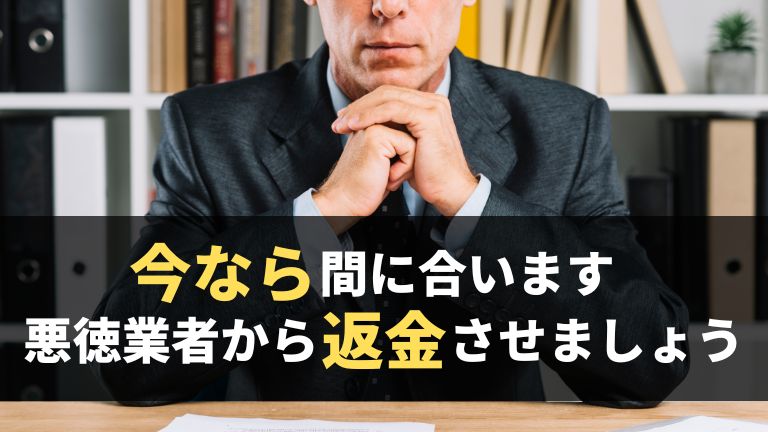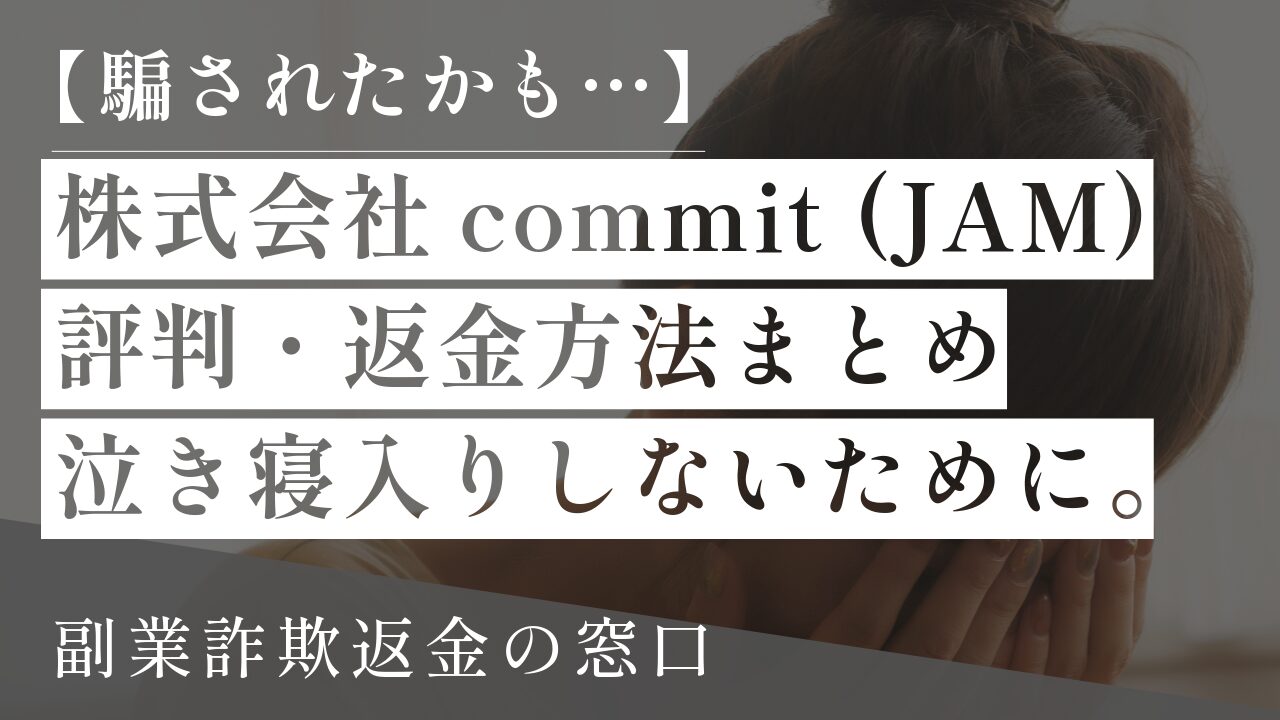株式会社GIVEのIT副業は詐欺なのか?画像タップで月収30万円は嘘?返金方法と対策
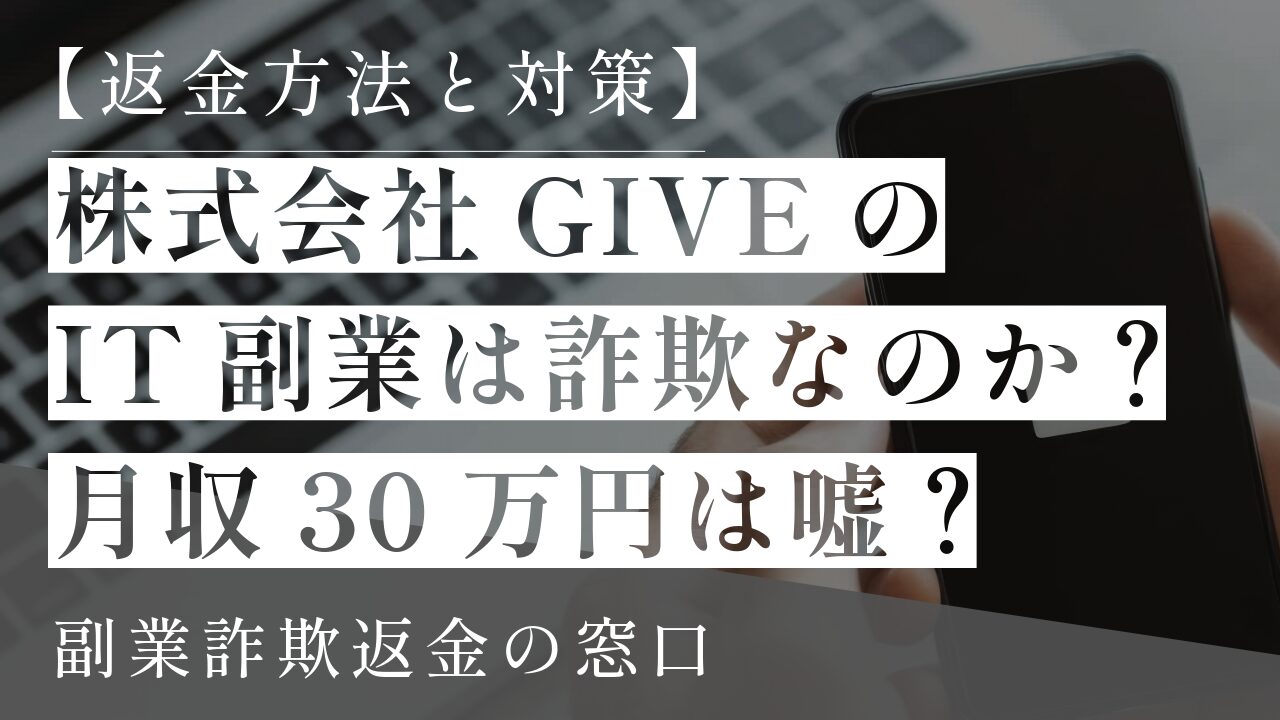
⚠️ 警告:株式会社GIVEの「IT」副業に注意! ⚠️
株式会社GIVEの「IT」副業は詐欺の可能性が極めて高いです。
「スマホで画像をタップするだけで1日3万円稼げる」という謳い文句を検証した結果、複数の問題点が判明しました。
この記事では、その実態と被害に遭った場合の対処法を詳しく解説します。
「簡単作業で高収入」と誘われて申し込んだけど、話が違う気がする…
マニュアル代は払ったけど、その後高額なコース契約を勧められた…
本当に稼げるのか不安だし、返金できるのか心配…
こんな疑問や不安を抱えていませんか?安心してください。この記事では株式会社GIVEの「IT」副業の実態と対処法を詳しく解説します。
目次
- 株式会社GIVEの「IT」副業の実態
- 危険な勧誘手口と高額請求の実態
- 会社情報と信頼性の検証
- 被害者の口コミと体験談
- 返金を求める方法と対処法
- 副業詐欺から身を守るための注意点
- まとめ:一人で悩まず専門家に相談を
1. 株式会社GIVEの「IT」副業の実態
株式会社GIVEの「IT」副業は、「スマホで画像をタップするだけで1日3万円稼げる」「作業時間はたった10分」「誰でも簡単に始められる」などと謳っていますが、実際にはこれらの宣伝文句は誇大広告であることが判明しています。
宣伝と実態の違い
宣伝内容
- スマホで画像をタップするだけの簡単作業
- 1日10分の作業で3万円以上の収入
- 今なら現金30,000円プレゼント
- 専門アドバイザーが無料レクチャー
実態
- 実際にはSNSを活用したアフィリエイト業務
- 画像をタップするだけで稼げるわけではない
- 30,000円プレゼントには条件あり(収益10万円達成が必要)
- 無料のはずが、高額なサポートプランの契約が必要
このように、宣伝内容と実態には大きな乖離があり、初心者が簡単に稼げるような仕組みにはなっていません。最初は1,980円のマニュアル代だけと案内されますが、その後に高額なサポートプランへの勧誘が待っています。
2. 危険な勧誘手口と高額請求の実態
株式会社GIVEの「IT」副業への参加者が報告している勧誘の流れは以下の通りです
勧誘の段階的手口
- 初期接触: LINEでの友達登録・無料説明
- マニュアル購入: 1,980円のマニュアル代金を請求
- 電話サポート: マニュアル購入後に電話勧誘が始まる
- 高額プラン提案: 「稼ぐためには」と高額サポートプランを提案
高額なサポートプラン料金
株式会社GIVEが提案する高額サポートプランの料金体系は次の通りです:
- Aプラン: 20万円
- Bプラン: 40万円
- Cプラン: 60万円
- Dプラン: 80万円
- Eプラン: 100万円
- Fプラン: 150万円
- Gプラン: 200万円
最も高額なプランでは200万円にもなり、中には650万円という法外な金額の報告もあります。こうした高額プランを契約しても、実際に稼げるかどうかの保証はなく、稼げないことが大半です。
3. 会社情報と信頼性の検証
株式会社GIVEの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社GIVE |
| 代表者 | 岡田隆太郎 |
| 所在地 | 東京都港区芝3丁目6-10 芝NAビル5F |
| 電話番号 | 03-4400-6394 |
| メールアドレス | company@give2000.com |
| 設立日 | 2024年6月18日 |
会社の信頼性に関する問題点
- 会社設立から間もない(2024年6月設立)
- 代表者の岡田隆太郎氏に関する情報がネット上に見つからない
- 企業としての実績が確認できない
- レンタルオフィスを使用している可能性
- 公式サイトが確認できない
会社の設立が非常に新しいことや、代表者の情報が公開されていないことから、信頼性に大きな懸念があります。このような特徴は、副業詐欺を行う業者によく見られるパターンです。
4. 被害者の口コミと体験談
ネット上で確認できる株式会社GIVEの「IT」副業に関する口コミはすべて否定的なものばかりで、実際に稼げたという声は一切見つかりませんでした。以下に複数の情報源から収集した口コミを紹介します
否定的な口コミ・体験談
マニュアル購入後の失望
「マニュアルを1,980円で購入したが、中身は初歩的なアフィリエイトの説明だけで、画像をタップするような仕事内容は一切なかった。ASPの開設方法など基本的なことしか書かれておらず、読む価値もないレベルだった」
勧誘の手法について
「『無料レクチャー』と謳っていたのに、実際には電話で高額サポートプランを勧められた。一番安いプランでも20万円で、最大200万円という法外な金額のプランまであった。焦らされるように『今だけ特別』と言われ、契約を急かされた」
プレゼントの条件
「現金30,000円プレゼントは条件付きで、商品受け取り後30日以内に10万円の収益を上げないともらえないことが後から判明した。これは事実上もらえないに等しい条件だった」
副業内容のギャップ
「画像をタップするだけと説明されていたが、実際はSNS運用によるアフィリエイト。フォロワーを増やして広告収入を得る手法で、初心者には難しすぎる内容だった。最初の説明と全く違うビジネスモデルだった」
高額請求の実態
「電話で『借金してでも始めるべき』と言われ、消費者金融からの借り入れを勧められた。『すぐに元が取れる』と説得されたが、実際に稼げる保証はどこにもなかった」
サポート体制の不備
「高額なサポート料金を支払った後、質問をしても返信が遅かったり、的外れな答えしか返ってこなかったりと、サポートの質が非常に低かった。お金だけ取られた感じがする」
返金拒否の経験
「思っていた内容と違ったので返金を求めたが、『デジタルコンテンツなので返金不可』と断られた。特商法にも明記されているとのことだったが、事前にそのような説明はなかった」
肯定的な口コミ
複数の情報源を調査した結果、「稼げた」「収入が増えた」といった肯定的な口コミや評判は一切見つかりませんでした。株式会社GIVEの「IT」副業で実際に収益を上げたという実証された例は確認できていません。
会社が2024年6月に設立されたばかりであることを考えると、実績を積んだ利用者がいない可能性が高いです。また、同様の手法で「画像選択で稼げる」と謳う副業は過去に複数存在し、それらも詐欺まがいとして注意喚起されていることから、同じパターンの可能性が高いと言えます。
5. 返金を求める方法と対処法
もし株式会社GIVEの「IT」副業に申し込んでしまった場合、以下の方法で返金を求めることができる可能性があります。
返金を求めるステップ
1. 証拠を集める
- 契約書やマニュアル、メールのスクリーンショット
- LINEやチャットの履歴
- 支払いの証明(振込明細など)
- 電話での会話内容のメモ
2. 相談窓口に連絡する
- 消費生活センター(消費者ホットライン:188)に相談
- 警察の相談窓口(#9110)に連絡
- 弁護士や司法書士などの専門家に相談
3. 法的根拠に基づく対応
- クーリング・オフ制度の利用(契約書面受領から8日間または20日間)
- 消費者契約法に基づく契約取消(不実告知や断定的判断の提供があった場合)
4. 返金交渉の実施
返金を求める際は、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。特に消費生活センターは無料で相談に応じてくれるため、まずはそちらに相談することをお勧めします。
6. 副業詐欺から身を守るための注意点
副業詐欺に騙されないために、以下の点に注意しましょう
- 簡単・高収入をうたう副業は疑う
「誰でも」「簡単に」「高収入」などの甘い言葉には要注意 - 実績や具体的な仕組みが説明されているか確認
どのようにして収益が発生するのか明確な説明がない場合は危険 - 運営会社の情報をチェック
設立して間もない会社や、代表者の情報が不明な場合は注意 - 口コミや評判を調査
ネット上で検索し、実際に稼げたという声があるか確認 - 高額な費用を要求される場合は慎重に
初期費用が安くても、後から高額請求がある可能性を考慮 - 個人情報の提供には慎重に
安易に個人情報を提供すると、二次被害のリスクがある
7. まとめ:一人で悩まず専門家に相談を
まとめ:株式会社GIVEの「IT」副業は危険
株式会社GIVEの「IT」副業は、「スマホで画像をタップするだけで稼げる」という誇大広告で人を集め、実際には高額なサポートプランを契約させる詐欺的な手法を用いていると考えられます。以下の特徴から、この副業への参加はお勧めできません
- 宣伝内容と実際の内容に大きな違いがある
- 会社の設立が非常に新しく、実績が確認できない
- 高額なサポートプランを契約させる手法が使われている
- 実際に稼げたという声が一切見つからない
もし既に契約してしまった場合は、一人で悩まず、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。時間が経つほど対応が難しくなるため、早めの行動が大切です。
最後に、副業で稼ぎたいと考えている方は、実績のある企業が提供するサービスや、具体的な仕組みが明確に説明されている副業を選ぶようにしましょう。
※ご確認ください※
本記事は、一般的な情報提供と注意喚起を目的として作成されており、特定の事業者やサービスに対する法的な評価(「詐欺」であるとの断定を含む)や、個別の契約に関する返金の可能性を保証するものではなく、法律相談を提供するものでもありません。具体的な事案に関するご相談や対応につきましては、必ず消費生活センター(188)または信頼できる法律の専門家(弁護士・司法書士)にご相談ください。